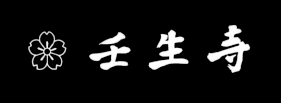正暦2(991)年の創建で、本尊は延命地蔵菩薩立像です。
「お地蔵さんのお寺」と親しまれ、節分行事や壬生大念仏狂言、厄除け等で信仰を集めてきました。
文久3(1863)年、結成当初の新選組が壬生に屯所を置き、当寺を兵法調練場としていたことから「新選組ゆかりのお寺」としても知られます。
境内の「壬生塚」には、新選組局長・近藤勇の胸像と遺髪塔、隊士のお墓や新選組顕彰碑などが建っています。
また、正門北側には、今も八木邸と旧前川邸(土日のみ一部公開)という、新選組屯所跡が現存します。
【 住 所 】 京都市中京区壬生梛ノ宮町31(京都市バス「壬生寺道」下車、徒歩約3分)
【電話番号】 075- 841-3381
【新選組逸話】
毎月4と9のつく日を訓練日とし、禁じられていた馬で乗り入れ、稽古をしていた。
訓練では、全ての門を閉じ、参拝者を締め出して大砲を打ち続けた。
大砲二門は、京都守護職の会津藩より得た。
寺は、毎月24日が本尊・地蔵菩薩の縁日にあたるため、訓練を25日に日延べするよう新選組に申し出ていた。
【主な年間行事】
節分会厄除大法会
2月2日~4日
京の年中行事の一つに数えられる壬生寺の厄除け節分会は、白河天皇の発願によって始められ、900年余もの永い伝統があります。
当寺は各社寺の中でも、京都の裏鬼門(南西)に位置し、京都の節分鬼門詣りの一端を往古より担っています。
期間中は各地より参詣する老若男女で、境内は大層賑わいます。
〇2月2日(水)/前日
厄除け祈祷会 山伏の大護摩祈祷 昇殿特別祈祷 厄除け鬼払い壬生狂言「節分」上演
〇3日(木)/当日
厄除け祈祷会 昇殿特別祈祷 厄除け鬼払い壬生狂言「節分」上演
〇4日(金)/後日
厄除け祈祷会
新選組隊士等 慰霊供養祭
7月16日 13:00〜
この日は祇園祭の宵山で、池田屋騒動が起こった日。これをトして、勤皇と佐幕の両志士を供養し、郷土の平安を祈る法要が行われます。一般焼香、尺八・武術の奉納などあります。
盂蘭盆 万灯供養会
8月9日~16日
9日の「精霊迎え」から16日の「精霊送り」まで、毎晩、本堂前に千灯以上が奉納されます。9日と16日には鉦鼓・太鼓・笛・囃子にあわせて踊る、六斎念仏の奉納もあります。
壬生狂言公開
2月2日・3日 / 4月29日~5月5日 / 10月の連休の3日間
700年余り前、壬生寺を大いに興隆した円覚上人が始めた「大念佛会」を始まりとし、「壬生さんのカンデンデン」と、京の庶民大衆に親しまれてきたものです。